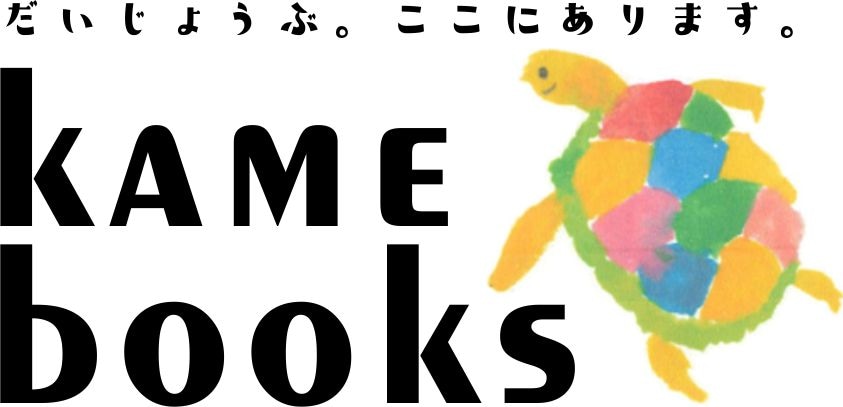-

ヤナイユキコ『朝ごはんのやり直し』※新本
¥700
暖かくてやさしい朝食の世界。 家族を見送ってからやり直す朝ごはん。 写真も素敵。 #ヤナイユキコ #朝ごはん
-
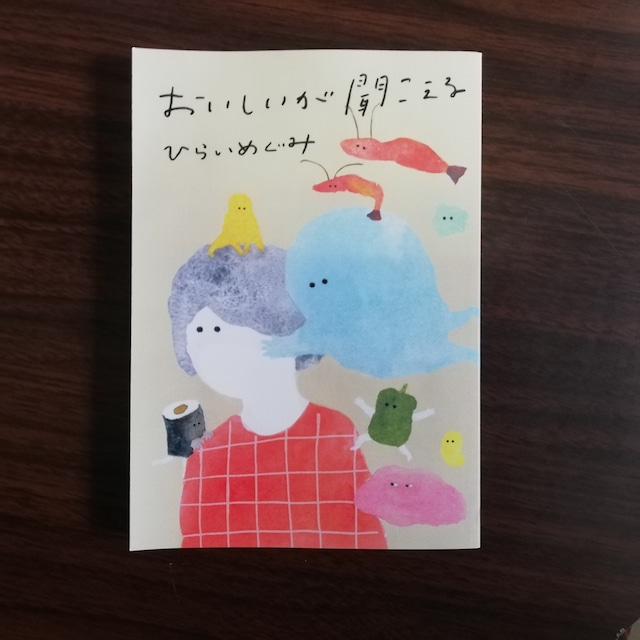
ひらいめぐみ『おいしいが聞こえる』※新本※サイン入り
¥1,540
SOLD OUT
たまごシールを集めている著者が綴るエッセイ。 食べながら、不思議に思ったり、想いだしたり。食べることは、自分に向き合うことかもしれない。そんな事を思います。
-
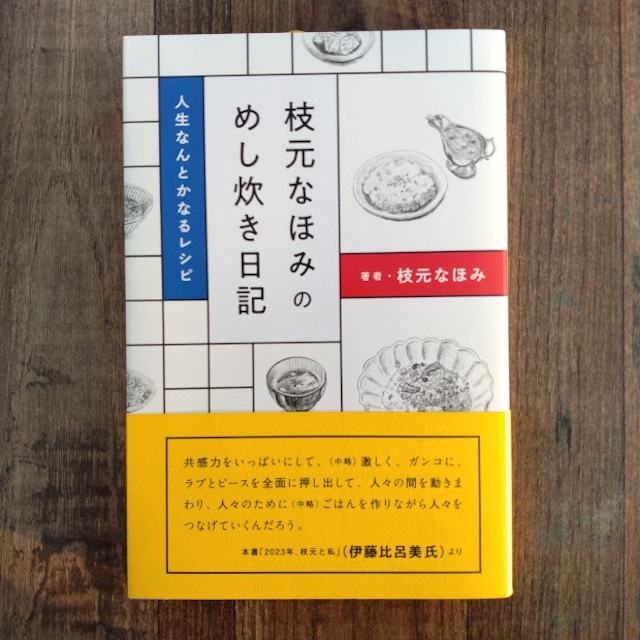
枝元なほみ『枝元なほみのめし炊き日記 ー人生なんとかなるレシピ』※新本
¥1,540
いろいろな人の人生に共感し応援する食を提案してきた自称「めし炊き」の著者が綴る18編のエッセイと30のレシピ。 子ども食堂で子どもたちがつくった、具を先に炒めておくひき肉チャーハン。 年末の炊き出し“大人食堂”に彩りを添えた炒めなます。 子どもの頃に家族で囲む食卓で、父の酒肴から少しもらっていたレンコンのニンニク炒め。 晩年にかつての家庭に帰りたがった認知症の父を思い出しながらつくる鶏胸肉の塩麹焼き……。 自身の病とも向き合いながら、謙虚にたくましくご飯を食べて生きて行くすべての人に贈るエール。
-

浅沼シオリ/早乙女ぐりこ/武塙麻衣子『三酒三様』※新本
¥1,100
SOLD OUT
酒好きの女性3人が、酒にまつわる話を綴ったZINE。 酒を呑みながら、読みたくなります。
-

テキスト 長井史枝/イラスト 井上彩『菓の辞典』※新本
¥1,650
ラムセス3世が楽しんだであろうBC時代のものから、近現代のティラミスやパフェまで。 約130種の西洋菓子の起源と痕跡を探り、描きおろしイラスト約100点とともに紹介します。 人から人へ、国から国へ 十字軍が遠征したり、王族の子女が他国にお嫁に行ったりすると、それにともない、お菓子も移動し発展していたのです。 お菓子一つひとつが持つストーリーを、古代から現代へと並べて掲載。 ページをめくるたびに現代へと近づき、まるで「お菓子」で時代を旅する気分になります。「お菓子MAP」やお菓子にまつわる「人物index」、レシピやペアリングのページも。 この楽しくてロマンチックで美味しい西洋菓子の本を読みながら、「飲み物だったチョコレートを固めようと思ってくれてありがとう!」「プリンから脂身を取り除き甘いお菓子にしてくれてありがとう!」「ガスパリーニさん、メレンゲを考案してくれてありがとう!」などと、何度も御礼を言ってしまうことでしょう。
-

ヴィトルト・シャブウォフスキ/芝田文乃 訳『独裁者の料理人:厨房から覗いた政権の舞台裏と食卓』※新本
¥3,300
歴史の重要な瞬間に彼らは何を目にしたか? 20世紀の独裁者5人に仕えた料理人たちの悲喜こもごもの人生。2021年度〈グルマン世界料理本賞〉受賞作。 著者はあるとき、ユーゴスラヴィアの独裁者チトーの料理人についての映画を見て、歴史上の独裁者に仕えた料理人たちに興味を抱く。そしてついに本物の独裁者の料理人を探す旅に出る。 本書に登場する独裁者はサダム・フセイン(イラク)、イディ・アミン(ウガンダ)、エンヴェル・ホッジャ(アルバニア)、フィデル・カストロ(キューバ)、ポル・ポト(カンボジア)。彼らに仕えた料理人たちは、一歩間違えば死の危険に見舞われた独裁体制下を、料理の腕と己の才覚で生き延びた無名の苦労人ばかりである。著者はほぼ4年かけて4つの大陸をめぐり、たとえ料理人が見つかっても、説得してインタビューに応じてもらうまでが一苦労で、なかには匿名で取材に応じる人もいた。 インタビューを再構成する形で料理人たちの声が生き生きと語られ、彼らの紆余曲折の人生の背後に、それぞれの国の歴史や時代背景が浮かび上がる。各章にレシピ付き。
-

粕谷浩子『地元に行って作って食べた日本全国お雑煮レシピ』※新本
¥1,430
SOLD OUT
人の家のお雑煮を食べ歩くお雑煮研究家、粕谷さんは、「お雑煮ほど面白い料理は他にない!」と言います。 お雑煮は「年に一回正月にだけ食べる料理」という位置付けで、飲食店で食べることはほとんどなく、家族や親戚と過ごす時間のなかだけで守られ育まれた閉ざされた料理。 しかし、粕谷さんは、 人に聞くと「自分の家ではこうだ!」と盛り上がるお雑煮談義に興味をもち、地域色の豊かさや奥深さに心ひかれ、好奇心に従って研究を開始。 じつはこんなにバリエーションがあるんだということを知ってほしい、いろんな味を食べ比べて欲しいと、お雑煮のよさを広めるため日々活動しています。 この本は、その粕谷さんの活動と、その突撃取材で入手した貴重なレシピを紹介する本です。
-

赤坂憲雄『奴隷と家畜 ー物語を食べる』※新本
¥2,640
生きるために、捕って、殺して、わたしたちは食べる。 食べるために、作物を栽培し、家畜を飼育し、人を奴隷にする。〈食べるひと〉ははてしない謎を抱いている。誰ものぞこうとしなかった意識の森深くへと、異端の民俗学者が下りてゆく。 物語を食べ散らかすような、不遜にしてスリリングな旅。
-

玉子区木耳町内会『町中華の宝石 きくらげたまご』※新本
¥1,650
町中華本は多い。が、そのほとんどはお店のガイド本だ。本書は、ひとつのメニューを通して、日本における町中華文化を探訪する試み。町中華を感じさせるメニューとは何か。 それは「きくらげたまご」(木耳と卵の炒め=木須肉・ムースーロー)である。きくらげたまごは、扱っている店とそうでない店があるが、定食にしてよし、単品でつまみにしてよしの、ナイスな料理だ。主に乾燥きくらげを用いるが、店によってテイストが異なる。そして、これが人気メニューという町中華店は意外に多い。 高級な中華料理店ではほとんど見かけない。あくまでも大衆料理店のメニューだ。しかも、めちゃくちゃメジャーな存在でもない。が、町中華を愛する人なら気になるメニューであり、深掘りしがいがある。最近では、コンビニでも総菜のひとつとして、回鍋肉や麻婆豆腐の横にそっと置かれている。静かなブームは到来しようとしているのだ。
-

繁延あづさ『山と獣と肉と皮』※新本
¥1,760
「かわいそう」と「おいしそう」の境界線はどこにあるのか? 山に入るたび、死と再生のダイナミズムに言葉を失いつつも、殺された獣を丹念に料理して、一家で食べてきた日々—。 獣を殺す/料理する/食べる。 そこに生まれる問いの、なんと強靭にして、しなやかであることよ。 いのちをめぐる思索の書。 母として、写真家をして、冒険者として。 死、出産、肉と皮革を、穢れから解き放つために。—赤坂憲雄氏、推薦!
-

グラフィック社編集部 編『ローカルおやつの本』※新本
¥1,815
SOLD OUT
ポンとひとくち頬張れば、たちまち幸せがやってくる! 全国各地のスーパーや菓子店で気軽に購入できる、日常のおやつ。 本書では、そんなお菓子や飲み物を約250点集めて紹介しています。 一つ一つにその土地や時代と深く関係した誕生の物語があり、また、つくり手たちの創意工夫があります。 日本の豊かなおやつ文化の一端に触れることができる一冊です。
-

溝呂木一美『ドーナツの旅』※新本
¥1,760
SOLD OUT
全国のおいしいドーナツ大集合! およそ10年前からドーナツの食べ歩きを始め、以来、年間500種類を食べる“ドーナツ探求家”の著者が、選りすぐりのドーナツ&店をたっぷり紹介。 現在、“第三次ブーム”の到来と言われる日本のドーナツ界ですが、そのトレンドを牽引する人気店から、長年地元で愛されるお店まで、著者が自らの足で集めた名店ばかりです。 また、ドーナツの歴史・種類などの基礎知識や、ご当地パンメーカーが作る名物ドーナツ、ミスタードーナツ特集など、日本のドーナツ文化を知るのに欠かせない情報も収録しています。 ドーナツから膨らむ幸せを堪能できる一冊です。
-

森岡督行『ショートケーキを許す』※新本
¥1,870
ふわふわのスポンジと生クリームと苺。この「日本型ショートケーキ」は、およそ100年前に日本で生まれ、今日まで独自の進化を遂げてきました。 本書は森岡書店代表の著者が、ショートケーキを愛するもの=「ショートケーキ応援団」として綴る、書き下ろしエッセイです。登場するのは25店のショートケーキ。一つひとつのショートケーキをいただく度に、物語が広がります。ショートケーキのまわりにある出来事、人物、建築、完全な思い込みによる妄想などなど。 100年前から私たちの時間に寄り添ってくれているショートケーキ。ショートケーキとは何か?コラム「日本型ショートケーキの誕生」ではその起源に関する新たな資料も出現!ショートケーキのまわりにある時間をご堪能ください。
-

オオヤミノル『喫茶店のディスクール』※新本
¥1,870
SOLD OUT
われわれは一体誰と契約をしているのか? SNSとグルメサイト、クラウドファンディングと ポイントカードに骨抜きにされた 消費者万能の暗黒時代に模索する「いい店」の条件。 自身の迷走を振り返りつつ、犬の目線で語る、経済、仕事、メディアにコミュニティ。 金言だらけの与太話再び。
-

オオヤミノル『珈琲の建設』※新本
¥1,870
野蛮なエスプリと高邁な屁理屈で語り尽くす、 珈琲の技法、美味しいの境界線、喫茶店という文化。 読むものを挑発し、苛立たせる、堂々巡りの 「反=珈琲入門」。
-

ロアンヌ・ファン・フォーシュト『さよなら肉食──いま、ビーガンを選ぶ理由』※新本
¥2,420
SOLD OUT
旧来の経済モデルと生活習慣が機能不全に陥った今、求められる新しい「食の物語」とは? 人口増・気候変動・環境汚染に歯止めをかける “ビーガニズム” の合理性と未来を解き明かすオランダ発の注目ノンフィクション。
-

橘真『哲学するレストラトゥール ー自給自足の有機農業で実践する「贈与への責務と返礼」』※新本
¥1,980
神戸の名ソムリエが淡路島に移住して実践する、有機農業による自給自足。 オルタナティヴな営みの実践を通して導く、ラディカルな手づくりの哲学と思想のカタチ。 かつての神戸を代表する伝説的なフランス料理の名門として一時代を画した[レストラン・ジャン・ムーラン]のソムリエを経て、闊達でフレンドリーな店として人気を博したワインバー「ジャック・メイヨール」の店主であった著者の橘 真さんは、その後、フランス・イタリアのワインや野菜の生産地を視察研修の後、ワインの輸入卸業務店を経て、2009年に淡路島に移住。 自らの思考と哲学を実践すべく、有機野菜の栽培、平飼いの養鶏による飼料の自給、罠と銃による狩猟などを行いつつ、淡路島内外のレストランに野菜などの直接販売を手掛けており、将来的には葡萄の自家栽培による有機ワインの醸造を目指しています。 都市的生活から一転、地方の中山間地に移り住み、「有機農業による自給自足」という、等価交換的価値観が蔓延する現代日本におけるオルタナティヴを選択し、自らの農業を「自然からの贈与に対する責務と返礼」と考えるその暮らしのカタチには、これから縮小していくのが既定路線であるこの国で生きるための知恵が隠されているように思います。 農業に興味を持ち地方へと移住する若者が増えつつある今、現代の日本社会の歪み、農業や地方が抱える問題と向き合いながら、農業や私たちの食、共同体、自我と隣人、人間存在や生きていくことの本質を、レヴィ=ストロースや網野善彦、オルテガなどの古今東西の知の巨人の思想にも言及しつつ、掘り下げて述懐します。 無償の贈与に対する責務の返礼を負ったレストラトゥール(レストランの職人)としての矜持を胸に、1人の農業家が自らの実践を通して導く、ラディカルな手づくりの哲学と思想がここにあります。
-

藤原辰史『 [決定版]ナチスのキッチン ー「食べること」の環境史』※新本
¥2,970
SOLD OUT
国民社会主義(ナチス)による支配体制下で、人間と食をめぐる関係には何が生じたのか? この強烈なモティーフのもと、竃(かまど)からシステムキッチンへ、近代化の過程で変容する、家事労働、レシピ、エネルギーなどから、「台所」という空間のファシズムをつぶさに検証し、従来のナチス研究に新たな一歩を刻んだ画期的な成果。 第1回(2013年度)河合隼雄学芸賞を受賞した、著者の代表作。
-

早川ユミ『畑ごはんーちいさな種とつながる台所』※新本
¥2,860
高知の山のてっぺんに住む早川ユミさん。 「北京風餃子」「玉ねぎラーメン」など子連れでのアジア旅を経て、家族のためにつくり続けてきた畑の野菜を使った春夏秋冬のレシピ集。 畑にまつわる話、循環する台所と道具の話、調味料、紅茶、梅干しづくりなども紹介。
-

蕪木祐介『チョコレートの手引き』※新本
¥1,760
知っているようで知らない魅惑の嗜好品、チョコレート。 どうやってできているのか?どう楽しめばよいのか?あらゆる知的好奇心を満たす本。 一本の木に実るフルーツのカカオが、一体どのように加工されてチョコレートになるのでしょう? 本書ではその全工程を写真とイラスト満載で詳しく解説。また、チョコレートの歴史、カカオの主要生産国を豊富な資料とともに紹介しています。数々の生産地を巡る著者による、ペアリングやドリンクレシピなどチョコレートの愉しみ方のコツもお教えします。 奥深いチョコレートの世界をすみずみまで知ることができる、まさにチョコレートの手引書のような一冊です。
-

『フルーツパーラーゴトー・フルーツパフェ溺愛誌 パフェ沼』※新本
¥1,980
パフェを溺愛する作家・クリエイターが集結。 フルーツパーラーゴトーのフルーツパフェだけを紹介し、論じるかつてない本が誕生しました!カバーのその「沼」を覗き見るような特製カバーで広げるとポスターにもなります。
-

『mg. vol.5 ドーナツをめぐる』※新本※栞付き
¥900
SOLD OUT
一冊、まるまるドーナツのZINE。 ドーナツアクセサリーを作ったり、美味しいドーナツを求めて歩き回ったり。
-

『ミスドスーパーラブ』※新本※特典ステッカー付
¥1,650
SOLD OUT
あなたの好きなミスタードーナツは何ですか? 僕は、オールドファッションです。 ミスドに愛を叫ぶアンソロジー。 豪華クリエイター陣によるグラフィック、短歌、小説、童話、エッセイ、ヴィジュアル作品で表現されたドーナツ、パイ、飲茶など26のメニューが収録。 おやつのお供にぴったりな一冊。ミスドに行く前にも行った後にも。
-

蒼井倫子『「いただきます」の人類史』※新本
¥2,200
わたしたちの身体は、食べ物でできています。単細胞生物が多細胞に変化しアミノ酸を外から確保し始めたときに、「いただきます」の歴史が始まりました……。 それから数億年が経ち、近い将来、大量生産と大量消費という食を取り巻く現在の構図は崩壊することが予想されています。 それは私たちの健康どころか、命そのものを脅かします。 食育を専門とする小児科医が、細胞や栄養素というミクロな世界から、いま人類を覆っている飽食と飢えの格差・生活習慣病・偏食といった大きな視点まで、ごはんと人の歴史をめぐる。